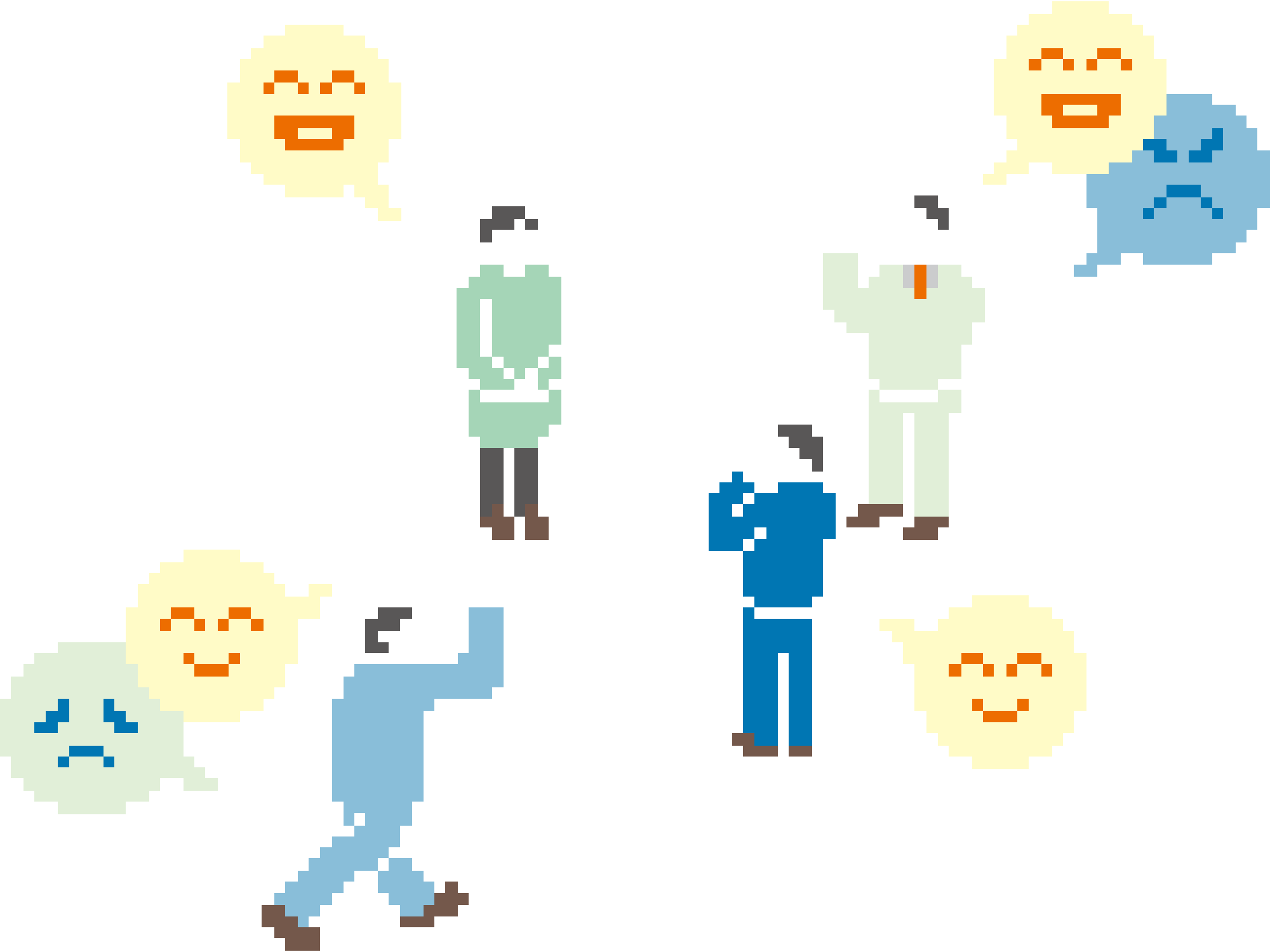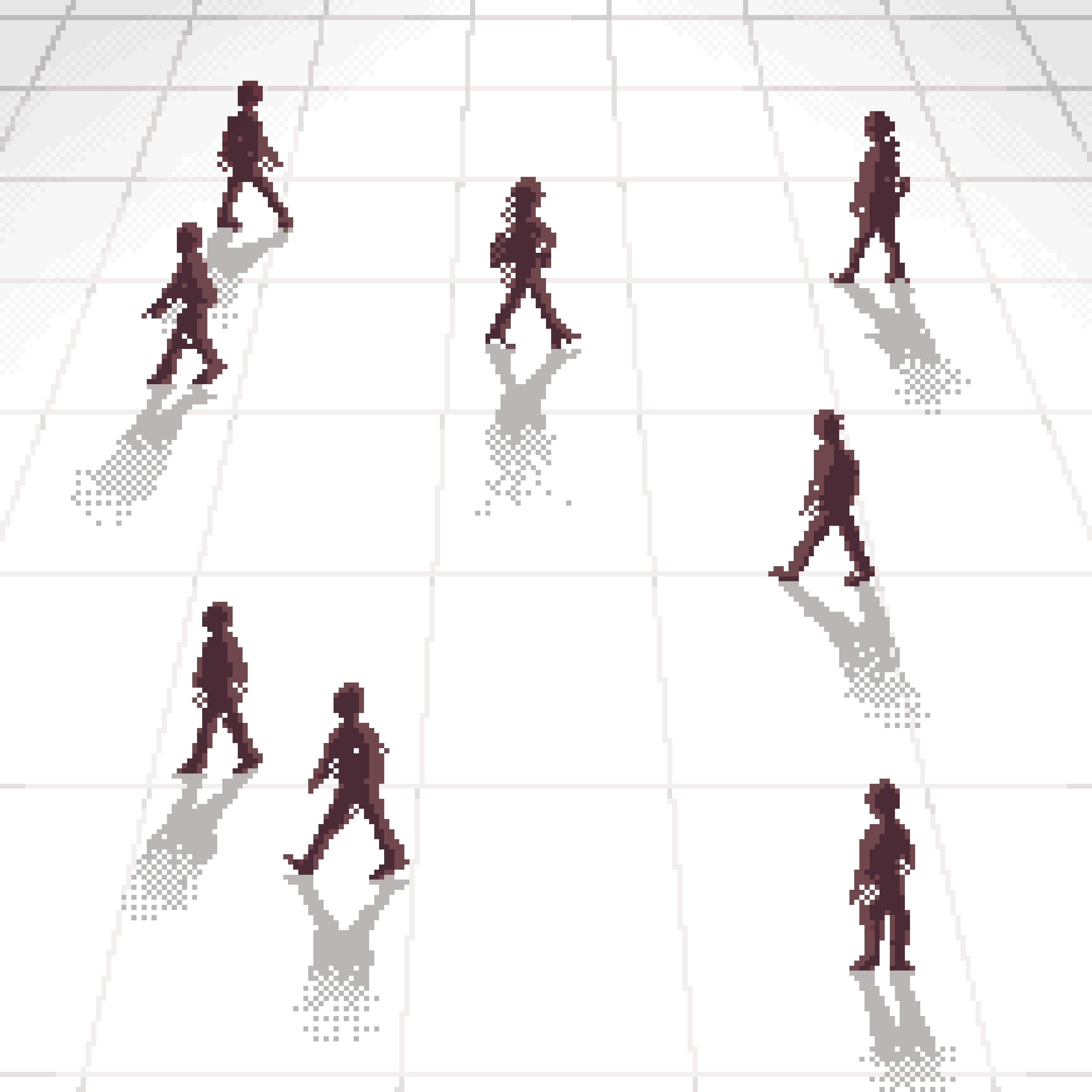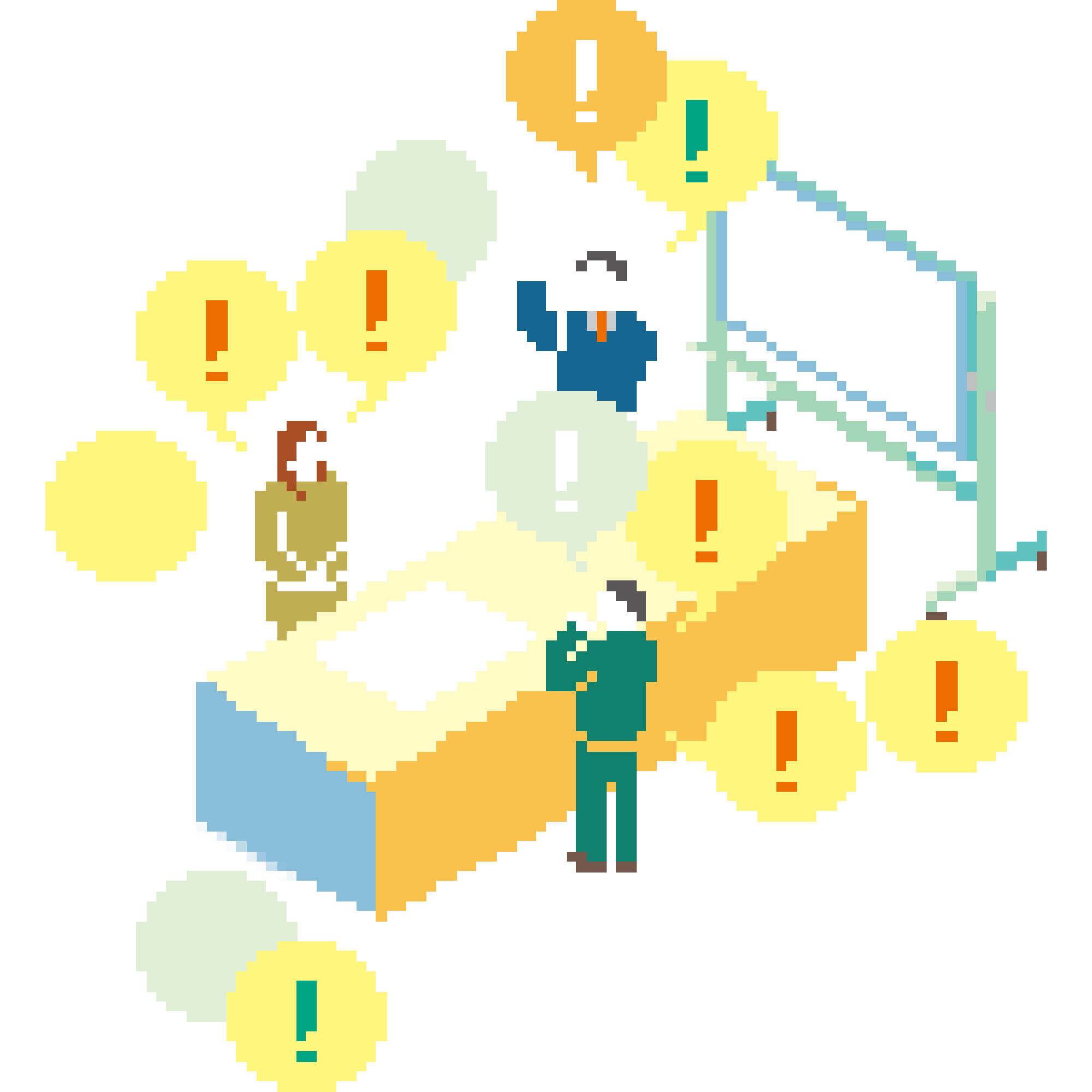パンデミックから5年。出社要請に反発が続く米国とは対照的に、日本のワーカーは能動的にオフィスへ戻り始めています。しかし、「オフィス回帰」は、必ずしも「組織への回帰」を意味していないことが見えてきました。
ワーカーが求めているのは、組織の空気に「馴染む」ための出社でありながら、人間関係の摩擦を避けて「個」に閉じるスタイルです。ハラスメントやストレスを避けて「固定席」や「馴染みの仕事」という安全地帯を求め、困りごとは同僚ではなくAIに相談する。充実は私生活に委ね、職場では「ドライな従順さ」を保つ。その姿は、自己責任や自己実現といった重圧から身を守るために、あえて労働を「他人ごと」へ変質させる防衛反応のようにも映ります。かつてオフィスで交わされていたような生々しい協働や衝突を、まるで遠い世界の出来事のように眺める。労働が「フィクション」化しているのかもしれません。これでは、経営層がオフィス回帰に期待した、身体的でリアルな協働は生まれないでしょう。
では、「フィクション」から「リアル」へワーカーを引き戻すにはどうすればよいのでしょうか。今回の分析を通して見えてきたヒントは、オフィスを「クラフト(実験)」の視点で再定義することにあります。
「クラフト」をワークプレイスに持ち込んだ好例があります。オランダのMiro社では、従業員が
日常的にオフィスの使い心地や要望をフィードバックする仕組みを構築し、3カ月ごとに空間のアップデートを繰り返しています。また韓国のNaver社では、オフィスを
「テストベッド(実験場)」と捉え、従業員や入居するスタートアップが
開発中の技術やアイデアを自由に実装しています。(参照:『
Global Workplace Review #2, #4』)
重要なのは、与えられた環境で働くだけでなく、自分たちの手で環境を「変えられる」という感覚です。オフィスを実験場として使いこなし、主体的に再構築する試みは、職場における「手触り感」や「手ごたえ」を養います。その身体的な実感が、労働を「他人ごと」から「自分ごと」へと転換するのではないでしょうか。
自分たちの手でオフィスをつくり変える。組織風土や従業員の変化に合わせて、オフィスは新たな姿へとクラフトされていくでしょう。その試行錯誤のプロセスと変遷は、
組織とワーカー固有の「思い出」として空間に刻まれます。特に日本人は、
職場での「遠い過去の思い出」によって幸福を感じやすい傾向があります(参照:『
同調から個をひらく社会へ』)。効率性や生産性の追求も大切ですが、そうした共有体験を生み出し、蓄積する
「記憶をアーカイブする場」としてオフィスを捉え直してみる。それこそが、希薄化した職場にリアリティを取り戻し、組織や同僚との未来のウェルビーイングとなるはずです。